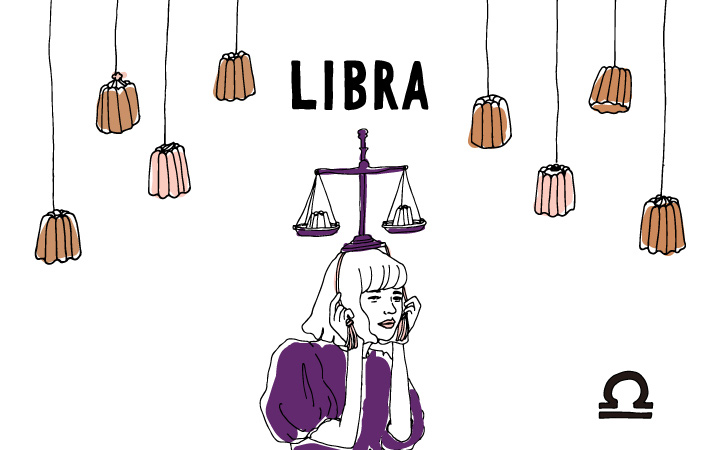国立新美術館にて開催された展覧会「ミュシャ展」など、数々の展覧会を手掛けてきた本橋弥生さん。国立新美術館の主任研究員肩書を持つ本橋さんの職業は、ひとことでいうと「学芸員」。「学芸員」って一体どうやってなるの? そして具体的にはどんな仕事をしているの? 本橋さんの場合について、教えてもらいました。
>>【関連記事】「ミュシャ展」大ヒット!担当者が語る、プロも苦心した巨大展示成功までの道のり

「学芸員」って何をしているの?
――美術館の学芸員というのは、どういうお仕事をしているんですか?
本橋弥生さん(以下、本橋) 日本だと学芸員は、展覧会の企画、調査・研究、実際かたちにするまで、何から何までやるという感じです。
――国立新美術館の学芸員の方は何名くらいいらっしゃるんですか?
本橋 当館の場合は6人です。学芸員以外のスタッフも含めると、非常勤の方を含めて40名、常勤職員はそのうち半数くらいでしょうか。国立新美術館の展示室の面積の合計が14,000㎡という会場規模だと、海外なら何百人いるはずなんですが、当館は非常に少ない人数で運営しています。
――すごく少ない感じがしますね! 展示を行うまでの流れはどのようになっているんですか?
本橋 国立新美術館は、多様な創作活動を紹介し、アートに親しんでいただくのを目的にしているんですね。ですので、近代美術が多くはなるのですが、現代美術やデザイン、ファッションなども取り上げています。まずは企画会議で学芸員が企画を持ち寄って「いつ、こういう展覧会をやりたいです」というのを挙げつつ、外からいただいた話も加えて検討しつつ、スケジュールを立てていく流れです。
――ミュシャ展はずいぶん長いプロジェクトだったと伺いましたが、それは特殊として、通常はどれくらい前から企画を立てているんですか?
本橋 現代美術の場合は1年くらいでどうにかまとめるものもあるのですが、通常は最低でも2、3年かけて進行しています。なので、同時に複数の企画が動いていたり、その人でないとできない仕事というのが多くて、学芸員はなかなか職場の異動ができないんですよ。
――外からのお話も「〇〇さんに担当してほしい」というのがあるでしょうし、属人的な部分が大きいんですね。本橋さんはそもそも、どうやって国立新美術館で働くようになったんですか?
本橋 大学を卒業した後に、大学院で美術史を専攻しました。その間、ハンガリーやフィンランドに留学をして、博士課程を修了する前に、2003年に国立新美術館の準備室が立ち上がったタイミングで運よく就職が決まり、働くことになりました。その後、2007年に開館して今に至ります。
――学芸員の資格自体は、比較的取得しやすいけれど、就職先を見つけるのが大変だと聞きました。
本橋 そうですね、どこかの美術館で誰かが辞めました、となって空きの募集がかかるので、美術館で働きたい人は東京にこだわらず、全国どこでも受けにいっている状況だと思います。
――何をしていたら就職しやすい、などはあるんでしょうか?
本橋 私の場合、たまたま国立新美術館の開館があったので運よく準備室から入れましたが、そうでなかったら今でも学芸員としては職がなかったかもしれないです(笑)。というのは、私が大学院で専門に研究していたのは東欧や北欧なのですが、美術館への就職となると、それぞれ美術館のコレクションや、みんなが見たいジャンルの専門知識を持った人が求められるので、圧倒的にイタリアやフランス、そして日本の美術を研究しているほうが有利になりますね。そういった事実について、大学院のときには全然知らなかったです。あと語学力は重要です。英語は必須で、プラスもう1言語できると良いですね。
――そもそもなぜ、東欧の美術史を選択されたんですか?
本橋 大学院のときには、フランスやイタリアを研究している人がすでにたくさんいるので、新しいことを発表できる気がしなかったんです。人がやっていないことで、研究して面白いことがないかなと考えていたときに、89年のベルリンの壁の崩壊が、中学生心に印象が強かったことを思い出しました。調べてみると、やはり閉鎖されていた時代が長かったので、東欧の美術の情報というのはあまり外に出ていなくて。ミュシャのスラヴ叙事詩を発見したのと同じように、実はこんな面白い美術品がありましたっていうのをまとめていくことは、ほかにやっている人がいないから、私にもできるかなと。研究しがいがありました。
――本橋さんが、フランスやイタリア、日本の美術史を専門に研究せずに、国立新美術館に採用されたのはなぜだったんでしょう?
本橋 正直よくわかりません。この国立新美術館は、所蔵品を持たない珍しい美術館なんです。いろいろな美術表現を取り上げていきますというコンセプトがあったから、私みたいな変わり種でも採用してもらえたんじゃないでしょうか。私はたまたまラッキーだったと思うので、基本としては、その美術館にある所蔵品やそれに近いものを研究していたというのは、大事な要素だと思います。あとは人間力でしょうか。どの仕事でも同じだと思いますが、コミュニケーション能力やプロジェクトの全貌をイメージし、完成に向けて必要なことを想像し、実行していく――そんな力は重要だと思います。
企画を考えるアンテナの張り方は?
――先ほど、学芸員の方が企画を持ち寄って展示を検討するというお話がありましたが、美術とひとことでいってもすごく広く、情報もたくさんある中で、学芸員の方はどうやってやるべきテーマを見つけるアンテナを張っているんですか?
本橋 基本はやっぱり足を使って実際に作品を見に行く、ですね。なかなか全部は難しいですが、なるべく見るということは大事です。これから現代美術を担当するぞと思ったら、画廊巡りをしたり、若くて最先端を求めたいときは、美大の卒業制作を見て回ったりもします。私の最近の関心はファッションやデザインに向いているので、展示されているものだけでなく、日常生活の中でも気になるものを探しています。
――国立新美術館では2017年7月5日から「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」が行われますが、パワーがあって面白そうだなと思う反面、現代美術ってどう見たらいいのか、難しいというイメージがあります。
本橋 昔の美術は、今日までにふるいにかけられているので、良いものしか残っていないんですよね。それに対し、現代美術は玉石混交というか、まだいろんなものが残っている。でも「今」を感じるライブ感のようなものが、何よりの魅力なのではないでしょうか。好き、嫌いといった感情が強くわき起こるのも面白い特徴だと思います。そういった粗削りさも含め、見ているときに「いまいちだなぁ」「なぜ?」と思う面白さもありますよね。今開催されている「草間彌生展」は、これをきっかけに現代美術を見てみようという人が多いと聞いています。ほかにどういう人がいるんだろうと興味を持っていただき、現代美術に親しむきっかけになるといいなと思います。
ディレクション能力も求められる学芸員
――私たちがふだん鑑賞している展覧会は、学芸員の方たちの感性と調査の集大成みたいなものですね。実際に展示を行うことが決まってから、どういった作業をされるんですか?
本橋 企画実施のための出品交渉や資金計画を立てるなど、環境を整えるためのさまざまな調整をするのはもちろんのこと、担当学芸員でないとできないことといえば、作品をどういうストーリーで見せていくかを考えることです。
――会場での作品の配置なども学芸員の方が考えるのですか?
本橋 そうなんです。就職するまで、学芸員は本を読んで調べて、ストーリーを書くだけなのかと思っていたのですが、まさか展示プランを構想することまで学芸員の仕事とは…。見せ方のようにデザイナー的な要素が必要とされるとは想像もしていませんでした。予算がない場合は、学芸員が展示デザイナーとなることもあります。デザイナーを別にお願いできる場合も、丸投げというのはなくて、こういう風に見せたいというアイデアを提示してから、それをさらによくするためのアイデアをもらって、よりよいプランを立てていくという共同作業になります。雑誌の編集と似ているかもしれません。
――確かに全体のストーリーをイメージして、それに向けて落とし込む作業をするという点では似ているかもしれません。でも雑誌はサイズが決まっていて平面ですが、美術館は空間な上に広大なので、もっと大変そうなイメージです(笑)。
本橋 私たちの場合だと、絵画の場合は平面なので、自力でプランすることが多いですね。彫刻やデザインなど立体作品になると、空間をみせることになるので、デザイナーさんの力を借りることが多いです。
――2016年に本橋さんが担当された「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」は、ファッションを美術の視点でとらえた、斬新な企画でしたね。
本橋 ファッションやデザインのもつクリエイティビティ――人の生活を豊かにしたり、変化させる想像力と創造力に興味があるので、そういった展覧会をもっと積極的にやれたらと考えています。海外ではすでにファッションやデザインがアートとして評価され、当然のように公立の美術館や博物館で作品が所蔵されています。国内でももっと文化的にも評価されるべきだと思っています。

――ファッションやデザインを文化的に捉える、というのも、国立新美術館らしい柔軟な美術の解釈ですね。
本橋 世界的な傾向ですが、最近は当館のように美術を幅広く解釈する美術館も増えてきています。そういう意味では、特定の美術史を学んでいないとダメ、というようながちがちのアカデミズムは少なくなってきている感じがしますね。もちろん、企画を行うにあたり専門の知識は必要となるので重要ですが、現代の事象をうまく分析してストーリーとして面白くわかりやすく伝える能力というのも、今後は評価されるのではないでしょうか。
*
外からは具体的なイメージがわきづらい「学芸員」というお仕事。知識もありながら、着眼点の鋭さや整理能力、創造性も求められるという、まさに専門職という印象です。
私たちが展覧会へ行くとき、これはどんな意図で何を伝えたくて企画されたのかということを、改めて頭に置きながら見ると、より楽しめるのではないでしょうか?

- TEXT :
- 本橋弥生さん 国立新美術館主任研究員
- 2019.1.18 更新
- クレジット :
- 構成/安念美和子(LIVErary.tokyo)